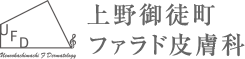水虫(白癬)について

水虫はとても身近な症状で、足水虫(英語:athlete’s foot、tinea
pedis)は5人に1人、爪水虫は10人に1人が持っているという報告もあります。また足水虫にかかっていてもかゆくなる方は10人に1人と報告されており、かゆみがない方も多くいらっしゃいます。足のかさかさや水ぶくれ、かゆみがなくても知らないうちに水虫になっていることがあり注意が必要です。
テレビコマーシャルで放映しており市販薬も多く発売されているため、市販のお薬で治療される方もいます。ただ水虫と思っていたのが水虫でなかったり、薬の成分でかぶれてしまい皮膚がじくじくしたり、かゆくなったりしてしまうこともあります。また中途半端な治療になってしまうこともあります。水虫を疑ったら、皮膚科を受診し菌が本当にいるか確認し治療していくことをおすすめしています。
水虫(白癬)の原因
水虫は医学的には白癬(はくせん)といいます。水虫(白癬)は、白癬菌というカビ(真菌)の一種が原因です。
白癬菌は、皮膚や爪、髪の毛の成分であるケラチンを栄養源にしているため、皮膚だけでなく爪や髪の毛にもついてしまい増えてしまいます。
白癬菌は高温多湿の環境を好みますので、靴や靴下で蒸れやすい足に多く水虫がみられます。また夏に水虫が多いのは、夏の暑さと湿度で白癬菌が増えるためです。足の裏は、サウナや銭湯、ジムなどで白癬菌がつきやすいことも足水虫が多い理由です。
足では水虫菌がつくと、24時間以内に皮膚に侵入することがわかっており、湿度が95%以上ですとわずか12時間で皮膚に侵入してしまうことも研究でわかっています。
水虫菌は、長靴の中で6ヶ月生きており、靴下でも3ヶ月は生きていることが研究でわかっています。さらに綿の靴下やストッキングを履いていても通過して皮膚につくこともわかっています。このように、白癬菌が付着した状態が続き、菌が増えやすい環境が整うことで水虫にかかります。
特にリスクの高い方は以下の方です。
- ブーツや革靴、靴下などを長時間履く方
- 足をしっかり洗わない方
- 糖尿病やがん、免疫が落ちている方
- 高齢の方
- ジムやサウナ、銭湯によく行く方
水虫(白癬)の症状と種類

水虫というと、足水虫だけを想像する方も多いのですが、足の爪や、頭皮、股、手など体のいろいろなところに症状が出ます。
白癬菌は皮膚に住みつくことが得意です。白癬菌が皮膚に住みだすと体の免疫が働き、菌を排除しようと炎症を起こします。皮膚に炎症が起こると、皮膚に皮むけ、赤み、かゆみ、痛みなど症状を起こします。これが水虫の症状です。
足水虫(足白癬)
水虫菌は、湿度が高く皮膚が柔らかい足の指の間から侵入してしまうことが多いです。最初は、赤みやかさかさ、かゆみ程度ですが、徐々に水虫菌が広がると足裏に水ぶくれを作ってしまうこともあります。水ぶくれを作る段階では、id疹といって全身に赤いプツプツがでてしまうような強い皮膚の炎症が起こることもあります。
趾間型(しかんがた)
足の指の間に発症するタイプで、水虫の中でも一番多いタイプです。小指と薬指の間にできることが多く、白くふやけて皮むけし、赤みやかゆみがみられます。
小水疱型(しょうすいほうがた)
足の裏や足のフチに小さな水ぶくれができて、一部は破れた後に乾燥してかさかさになります。
角質増殖型
角化型足白癬(角質増殖型足白癬)では踵ががさがさし、足裏の皮膚が厚くなりひび割れてしまうことがあります。痛みやかゆみは少ないことも多いです。水虫の顕微鏡検査でも見つけにくく、また治療も飲み薬が必要になることがあるなど手強いタイプになります。
爪水虫(爪白癬)
水虫菌が爪に侵入してしまった状態です。足の親指の爪によくみられます。
爪が水虫菌で壊され、白くにごり、もろくボロボロとなり、また爪が厚くなってしまうこともあります。爪は水虫菌にとって都合のよい環境で治療が少し難しくなります。爪に浸透しやすいぬり薬や、飲み薬を使って高い濃度のお薬を爪に届けることが必要になります。爪水虫にならないよう、爪に水虫がいかない早期に足水虫を治すことが必要です。
手水虫(手白癬)
多くの場合、手水虫は足水虫からうつります。高齢の方や足水虫の症状が強い方、手にステロイドを塗っている方にみられることがあります。
Two-feet-one-hand syndromeという言葉があり、これは両足の足水虫と片手の手水虫がよくみられるというれっきとした医学用語です。
体部白癬
“たむし”といわれるものです。足水虫が、股にうつってしまうことや背中など体のいろいろなところにでてしまうことがあります。股にできたときは股部白癬(いんきんたむし)と呼びます。体部白癬では、かゆみがあり、かさかさ円形の赤い発疹がみられます。湿疹と似ていますが、中心部のカサカサや赤みが少なく、周囲の赤みやカサカサが強いことが特徴です。
また足水虫はT. rubrumとT. mentagrophytesという白癬菌が95%を占めますが、イヌやネコにつきやすいM. canisというカビによりできる体の白癬もあります。M.
canisによる皮膚の症状は痒みや赤みが強いことが特徴です。若い方の境界くっきりした赤みではこの病気を疑い、ペットを飼っていらっしゃるかお尋ねすることがあります。
頭部白癬
“しらくも”と言われていたものです。お子さんに多く、頭の毛に水虫菌がついてしまい、境界くっきりの脱毛になってしまうことがあります。脱毛部分は、かさかさし髪の毛が短く切れています。更に進行してしまうと、Celsus禿瘡(ケルススとくそう)という頭皮の深いところに炎症が起こってしまい、赤くぶつぶつ、じくじくしてしまうことがあります。痛みが出て膿が出てしまうこともあります。
またレスリングや柔道など格闘技を行っている方は、T.
tonsuransという菌の集団感染がみられています。この菌は集団での治療が必要となります。
水虫(白癬)の検査

水虫菌は、肉眼では見えませんが顕微鏡によって拡大して見ることができます。足の裏や指の間のかさかさや水ぶくれ、白く濁った爪の一部をピンセットでとり顕微鏡で検査します。検査結果は5分ほどでわかります。痛みはほとんどなく、保険適用で検査できます。顕微鏡検査で白癬菌が確認できれば、水虫(白癬)の診断となります。
1回の検査で見つからないこともあり、症状の経過次第では何回か検査させて頂くこともあります。
水虫(白癬)の治療

足水虫は多くの場合、ぬり薬の治療でよくなります。1ヶ月ほど水虫のぬり薬をぬると足のがさがさやかゆみが消えていきます。しかし、見た目がよくなったこの時期に塗るのをやめてしまうと、まだまだ水虫菌が残っており再発してしまいます。水虫の塗り薬は少なくとも合計3ヶ月は塗ることが必要になります。
塗る範囲は、症状が出ているところだけでなく足全体に塗る必要があります。足裏・指の間・アキレス腱・足裏の縁です。症状がなくてもこの場所は両足ともに塗るようにします。なぜなら症状がなくても、逆の足にも水虫菌は必ずついているからです。水虫の塗り薬は薄めに伸ばして塗っていただき問題ありません。
このぬり薬(抗真菌剤)にはルリコン、アスタット、ニゾラール、ラミシールなどいくつか種類がありますが、どれもよく効きます。クリームタイプ、軟膏タイプ、液体タイプがあり、基本的には塗りやすいクリームタイプを使いますが、じくじくしている時は肌により優しい軟膏タイプを処方します。
副作用はまれにかぶれる方がいらっしゃいます。万一かぶれてしまった場合には、かぶれをステロイドの塗り薬で治療してから他の系統の水虫のぬり薬に変えます。市販薬の水虫薬も有効成分としては、処方薬と同様の成分を含んでいるものも多くあります。ただ、かゆみ止め成分やアルコール成分など皮膚に刺激になってしまう成分も含まれていることが多く、かぶれの原因になることがあり注意が必要です。
爪水虫(爪白癬)の治療
爪水虫は、爪に入ってしまいお薬が届きにくい状態になっています。そのため、少しでも効果が高いようにお薬が工夫されています。
足の爪は生え変わるのに時間がかかりますので治療も時間がかかるものとなります。すでに水虫で変形してしまった爪は元に戻らず、伸びてきた新しい爪がきれいになっていることで治療効果をみていきます。根気よく続けていきましょう。
ぬり薬としてはクレナフィンとルコナックという爪水虫の塗り薬が保険適用で使えます。爪への浸透が高くなるように工夫されており、クレナフィンやルコナックを塗ることで爪水虫が治っていきます。完全に治るケースは、1年間続けて20-30%程度で、半分弱の方にある程度の効果がでます。いずれにしても爪水虫には6~12ヶ月ほどの長い間治療が必要になります。場合によって、白くにごった水虫の巣をニッパーなどで取り除き、よりぬり薬の効果を高めることもあります。
また効果が高いお薬として、飲み薬もあります。ラミシール、イトリゾール、ネイリンという3種類になります。ラミシールというのみ薬は毎日1錠を6ヶ月以上続けます。イトリゾールというのみ薬は1週間薬を続け、3週間は休む、という1ヶ月の周期を3回、つまり3ヶ月行います(「パルス療法」と呼ばれます)。肝臓に負担がかかることがまれにありますので、採血を定期的に行いながら治療する必要があります。比較的新しい飲み薬としては、ネイリンがあります。12週間、1日1錠を飲むお薬となり、12週間を飲み終わっても効果が継続し爪水虫を治していきます。今までの薬より副作用も少なく、効果も高いことが研究でわかっていますので爪水虫の第一選択になることも多くなります。
頭部白癬の治療
水虫菌が髪の毛の毛穴に侵入してしまい、ぬり薬が届きにくいため飲み薬で治療します。
水虫(白癬)を放置するとどうなるか
水虫菌自体は皮膚より奥に侵入することはありませんが、足水虫によって皮膚に赤みやじくじくなどの小さな傷ができると、細菌がそこから侵入してしまい蜂窩織炎(ほうかしきえん)や壊死性筋膜炎(えしせいきんまくえん)といった感染症を起こすことがあります。
感染症をおこすと、痛みや発熱、悪寒を感じ、入院が必要になってしまうこともあります。特に糖尿病の患者では重症になりやすいため日頃から注意が必要です。爪水虫も進行すると爪が大きく変形し、痛みが出ることや、靴が履きにくい、歩きにくいなどの症状が出ることがあります。
水虫(白癬)のケアや予防について

足水虫にならないためのポイントは、①清潔にする、②乾燥させることです。
サウナやジム、プール、銭湯に注意
足水虫はバスマットや床からうつってしまいます。足の皮膚に水虫菌がついてから12~24時間で肌に住み着いて足水虫になってしまうので、サウナやジムに行った後は足を拭いたり洗ったりして水虫を予防しましょう。
家族や同居人が水虫の場合は注意
バスマットやスリッパ、床などから足水虫がうつってしまうため、家族で別にすることが大切です。素足で歩かないようにすることもおすすめです。家族内でうつしあってしまうこともありますので、家族で同時に治療することも重要です。
足の指や裏を優しく洗う
足の指の間もしっかり開いて優しく石鹸で洗うことが大切です。
水虫がうつりやすい環境に気をつける
水虫菌は温度15℃以上、湿度70%以上になると増えやすくなるので、足や靴を乾燥させ、長時間靴を履かない、5本指ソックスで指の間を乾燥させるなど対策が必要です。靴もよく乾かすことが大切です。
糖尿病の方は特に注意
糖尿病の方は免疫が落ちているために水虫になりやすい特徴があります。日頃から清潔に気をつけ足のケアをしていきましょう。
当院の特徴
当院では水虫の状態に合わせて診断・治療を行っています。水虫か心配な方や市販の水虫薬が合わなかった方など、お気軽にご相談ください。
【参考文献】
・仲 弥ほか:日臨皮誌、2009; 27: 27
・井出真弓ほか:真菌誌40:93,1999
・渡辺京子ほか:真菌誌41:183,2000
・望月 隆ほか:日皮会誌:129(13)、2639-2673、2019